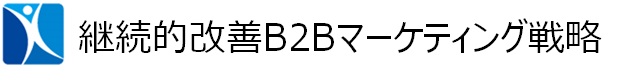継続的改善B2Bマーケティング戦略における改善フェーズとは

- 継続的改善B2Bマーケティング戦略における改善フェーズとは、今までのインプットを統合して「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供するかを作り上げることです
- それにより、あるべき姿の継続的改善B2Bマーケティング戦略を作り実行します
詳しくは以下のコラムで
継続的改善B2Bマーケティングの改善フェーズ
継続的改善B2Bマーケティングはリーンシックスシグマの改善手法であるDMAICという考え方を使います。DMAIC手法とは経営の効率や品質向上を目指すプロセスイノベーションのための手法で、リーンシックスシグマの基本となるものです。
■関連コラム
ここでは継続的改善B2Bマーケティング改善フェーズ(Improve)について説明します。
改善フェーズでは、まずSBUの見直しが必要かを考え、分析フェーズで取り出した根本原因や戦略課題を最適化する改善案、大きな視点からの課題、新しいアイデアなどを統合し「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供するか、つまりあるべき姿のB2Bマーケティング戦略を再設計し作りあげます。(図の⑧から⑫の部分)
- 改善案(最適化)(⑧)
- 大きな視点(⑨)
- 新しいアイデア(⑩)
- インプット統合・戦略再設計(⑪)
- 実行(⑫)

改善案(最適化)
まずは改善策をまとめます。(図の⑧)
分析フェーズでは、問題点を整理して、それぞれの問題点グループを根本原因(真因)のレベルまで分解しました。改善化とはつまり問題の根本原因を取り除く事です。問題点を根本原因のレベルまでしっかりと分解して、その根本原因を取り除くことで問題が解決されます。
さらには、問題点の解決策だけではなく戦略的な課題も見つけました。戦略的課題を取り出すために現状認識で理解した外部環境と内部環境をインプットとしてSWOT分析をします。SWOT分析を行うことで自社の強み、弱み、機会、脅威を理解することが出来ます。
SWOT分析が終わったら、それをインプットとしてクロスSWOTを行います。SWOT分析とクロスSWOTを行うことで戦略課題を取り出します。
根本原因を取り除く解決策と戦略課題をみつけたら、それぞれの影響度を検証し、優先順位付けを行いました。
その優先順位をづけした解決策、戦略課題が改善策であり、「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供するか、つまりあるべき姿のB2Bマーケティング戦略のベースとなるものです。
分析フェーズや、分析フェーズにおける根本原因の見つけ方、戦略課題の取り出し方については、以下のコラムを参照して下さい
■関連コラム
大きな視点で考えてみる
優先順位をづけした解決策はできましたが、あるべき姿の「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供するかの戦略を再設計する前に、より大きな視点でビジネス全体をみてみましょう。
最終的にB2Bマーケティング戦略を再設計する前に、より大きな視点でビジネス全体をみてみましょう。いくつかの視点を紹介します。(図の⑨)
まず戦略の基本的な考え方として、マイケル・ポーターの3つの基本戦略という考え方があります。これは自社が属する市場の中で持続できる競争優位を築くためには大きく3つの戦略にわかれるというもので、その3つは コストリーダーシップ戦略、差別化戦略、集中戦略となります。さらに集中戦略はコスト集中と差別化集中にわけることができるというものです。自社の戦略の方向を考えてみましょう。
次に大枠の戦略(グランドストラテジー)について考えてみましょう。大枠の戦略の考え方と、どのような戦略を取るのかを判断する方法を2つ紹介します。 1つはSWOTで行った自社の強み弱みと内部リソース外部リソースの活用からとるべき戦略を判断するグランドストラテジーセレクションマトリックスという方法です。もうひとつは、市場成長率と競合状態からとるべき戦略を判断するグランドストラテジークラスターという方法です。
詳しくは以下のコラムをご覧ください。
■関連コラム
新しいアイデアを出す
次に新しいアイデアを発想してみましょう。(図の⑩)
なぜならば測定フェーズでおこなった現状認識、そこから発見した根本原因の解決策や戦略課題は、基本的には過去からのアイデアであり、今までになかった全く新しいアイデアを発見することが難しいからです。アイデアの発想法にもさまざまありますが、いくつかを紹介します。
- オズボーンのチェックリストによる発想法
- 2×2マトリックスによる発法
- マンダラートによる発想法
- ブレインストーミング、ブレインライティングによる発想法
■関連コラム
インプット統合・戦略再設計
最終的に問題点や戦略課題を最適化する改善案、大きな視点からの課題、新しいアイデアなどを統合しマーケティング戦略を再設計し作りあげます。あるべき姿の「誰に」、「何を」、「どうやって」、価値を提供するかの戦略を再設計します。
戦略のの再設計に必要なインプット項目は以下に出揃いました。
- SBUミックス *再編成の必要があれば
- 改善案(問題点の根本原因と戦略課題を最適化)(図の⑧)
- 大きな視点からの発想(図の⑨)
- 新たなアイデア(図の⑩)
今まで取り出したこれらのインプットから「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供しているか」を再設計していきます。(図の⑪)測定フェーズで行った現状の「誰に、何を、どうやって価値を提供しているか」を“あるべき姿”に変えるプランを作ります。
以下がB2Bマーケティング戦略の構成です。この流れでプランを再設計します。

まず「誰に」を決めます。
誰にとは顧客(市場)は誰かを決めて競合との差別化を図っていく事になります。セグメンテーション、ターゲッティング、ポジショニング(STP)といわれる手順です。
簡単にいうと市場をいくつかの切り口でグループに分け(セグメンテーション)、そのなかから一つのグループを標的市場としてを選び(ターゲッティング)、選んだグループの中で競合とどのように差別化するかを決める(ポジショニング)ということを行います。
■関連コラム
「誰に」の次は「何を」を決めます。
「何を」とはどんな商品やサービスを提供して価値をあたえるかです。単に商品を売るのではなくサービス全体として価値を売り、どのようにその対価をいただくかが大切になってきています。
商品・サービスやその価格だけを決めれば良いということでなく、最終的には総合的なマーケティングミックスを作成するということになります。マーケティングミックスとは標的市場として設定した顧客(市場)のニーズやウォンツを満足させる為の価値を生む仕組みやツールの組合せです。
■関連コラム
最後は「どうやって」です。
「どうやって」とは、誰に(標的市場)、何を(どんな価値:マーケティングミックス)を提供するときに、どのようなマーケティングメッセージを、どのように伝えて(コミュニケーションして)、どのように実現する(サービスを届ける)かを決めるという事です。
つまり顧客獲得の仕組みとしてのカスタマージャーニー、顧客育成の仕組みとしてのカスタマーストーリー、そして顧客維持の仕組みとしてのカスタマーエクスペリエンスを再構築するということになります。
カスタマージャーニー、カスタマーストーリー、カスタマーエクスペリエンスを継続的に改善する方法は以下を参照してください。
■関連コラム
インプットを統合して戦略の再設計が終わり、あるべき姿の「誰に、何を、どうやって価値を提供するか」が決まったら、具体的なビジネスモデルとしてイメージしてみましょう。イメージ化することで頭の整理が出来ますし、企業内のコミュニケーションの役にも立ちます。いくつかの方法を紹介しますので参考にしてください。
■関連コラム
戦略を実行する
あるべき姿を実現するマーケティング戦略が完成したら実行に移します。(図の⑫)継続的改善マーケティング戦略の作り方で行った、定義、測定、分析、改善各フェーズのポイントをまとめることでマーケティング戦略書を作成して社内に共有することで全社の進む方向をあわせます。
実行にあたっては戦略から戦術へ(Strategy to Tactics)の落とし込みが必要です。
さらに再設計した、 「誰に」、「何を」、「どうやって」価値を提供するかを実現するための柱となる大枠の戦略プログラムをリストアップし、具体的な戦略プロジェクトの時間軸を決めて、タイムラインを3年程度のタイムスパンで落としこみ、具体的な戦略ロードマップのを描きます。
各プロジェクトの実行には、それぞれの戦略プロジェクトごとにプロジェクトチャーター(プロジェクト計画書)を作成しましょう。
実行の手順に関して詳しくは以下のコラムをご参照ください。
■関連コラム (リンクのないコラムは近日公開予定です)
改善フェーズが終わったら、次は管理フェーズです。

「図解!B2Bマーケティング戦略の作り方」eBook無料ダウンロード
マーケティング戦略とは、「誰に」、「何を」、「どうやって」提供して対価をもらうかということ。マーケティング戦略の基本をシンプルに理解できるeBookを無料で差し上げます。以下のフォームに記入して手にいれてください。