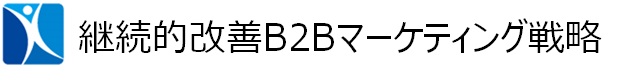KPIツリーで目標と進捗を管理する

- KPIツリーで目標と進捗を管理するとは、目標達成のストーリーを見える化することです
- それにより、実行したプランの進捗と結果を管理します
詳しくは以下のコラムで
KPIツリーは目標達成のストーリーを見える化したもの
目標を設定したら目標を達成するためのプランをつくって実行します。実行したらやりっぱなしではいけません。実行したプランが思ったように上手くいっているのか、それとも何かしらの問題があるのかを確かめる必要があります。そこで実行プランと連携したKPIツリーを作成することで進捗と結果を管理するのです。
KPIは目標ではなく、目標を計測する物差しです。たとえば全社の目標は売上100億円とした場合、設定した売上が目標(KGI)であり、KPIは売上金額です。KPIを金額ではなく成長率としたら、全社の目標は昨年より売上を10%あげるというような目標になります。
ですのでKPIを設定するのが目的ではなく、到達すべき目標の計測指標のKPIを決めて、目標の進捗を管理するということが目的になります。
改めてKGI、KSF、KPIの意味を確認しましょう。
- KGIは、Key Goal Indicatorで目標(目指すべき数値)
- KSFは、Key Success Factorで鍵となる成功の要因
- KPIは、Key Performance Indicatorで目標を達成するための計測指標(物差し)
KPIツリーとは、設定した目標(KGI)を実行プランの成功要因(KSF)で分解して、その成功要因を計測できる計測指標(KPI)を設定してツリー構造にして数値化し見える化したものです。
KPIを考える際には、KGI/KSF/KPIの順番で考えるとすっきりします。KGIとKSFとKPIの考え方について詳しくは、以下のコラムをご参照ください。
■関連コラム
継続的改善改善B2Bマーケティング戦略の目標を分解する
では継続的改善B2Bマーケティング戦略をKPIツリーで表してみましょう。継続的に改善することによって継続的に成長尾するのが継続的改善B2Bマーケティング戦略です。

まず一番左側に目標(KGI)を設定します。継続的改善B2Bマーケティング戦略の目的は企業のあるべき姿、ビジョンを実現することであり、その目標は継続的な成長です。KGIは数値である必要がありますので、継続的な成長を3年の中期戦略とした場合、3年連続で10%の成長というような数字にすることができます。
次に継続的成長の成功要因(KSF)は何かを考えます。言い換えると継続的成長は何によって成し遂げられるかを考えることになります。つまり実行プランのコアとなっている内容が成功要因になっているはずです。マーケティング戦略のコアは「誰に」「何を」「どうやって」ですが、この中でも「どうやって」という部分が実行プランのコアであり、「どうやって」をいかにプラン通りに効果的に実行できるかによって成否は右されます。継続的改B2Bマーケティング戦略では、カスタマージャーニー・カスタマーストーリー・カスタマーエクスペリエンスが継続的成長を支える成功要因KSFといえるのです。
継続的改善B2Bマーケティング戦略、継続的成長のKSFは
- カスタマージャーニー最適化 ー 最大効果最大効率で質の高い新規カスタマーを獲得すること
- カスタマーストーリー最適化 - 最大効果最大効率で攻めの営業活動を行うこと
- カスタマーエクスペリエンス(CX)最適化 - 最大効果最大効率のE2ECXを作ること
継続的改善B2BマーケティングのKPIツリーの図の中で、3つのKSFの進捗を確認するための計測指標であるKPIの第一階層がKPI-1です。
カスタマージャーニーのKPIツリー
ここからは、継続的改B2Bマーケティング戦略の成功要因KSFである、カスタマージャーニー・カスタマーストーリー・カスタマーエクスペリエンスのそれぞれを、さらに分解したKPIツリーを見ていきましょう。
以下がカスタマージャーニーのKPIツリーです。

カスタマージャーニーのKGIはマーケティングROIの最大化です。マーケティング活動をすることによって最大の投資対効果を得ることがゴールです。
そしてそれを実現する成功要因KSFは「顧客数の増加」、「LTVの増加」そして「費用の管理」です。(LTV:Life Time Valueは、顧客生涯価値のこと詳しくはこちら)
そして顧客数の増加というKSFの下には、それを実現するためのKPIがあります。KPI-1は「新規顧客数」や「離脱顧客数」、そしてKPI-1をさらに分解したものがKPI-2であり、新規コンタクト数(新規顧客獲得数)の場合には、カスタマージャーニーのプロセスである、「認知者数」、「リード数」、「プロスペクト数」、「カスタマー数」、「プロモーター数」というKPI-3があります。
このようにKPIツリーは分解できます。
例えば継続的成長のKPI‐1の新規顧客獲得数を目標(KGI)としてKPIツリーをつくることができます。この場合に今年の新規顧客獲得数を1万人という目標(KGI)として設定するとします。するとKPI-1は下の図ように「認知者数」、「リード数」、「プロスペクト数」、「カスタマー数」、「プロモーター数」となります。

すると認知者を何名獲得し、「リード数」を何名獲得し、「プロスペクト数」を何名獲得し、「カスタマー数」を何名獲得し、「プロモーター数」を何名獲得する必要があるかを決めていき、このKPI-1の目標を達成すると、その結果として、新規顧客獲得数を1万アカウントが達成できるというストーリーができあがるわけです。
おわかりでしょうか。KPIツリーでは、各階層の目標をKPIで設定し、そのKPIが達成されれば結果的に全体の目標が達成されるという構成になっていることが必要です。KPIツリーを作る際には、全体がストーリーがとなって構成されていることが大切になります。
このようにKPIツリーは分解できます。カスタマージャーニーについて詳しくは、以下のコラムをご参照ください。
■関連コラム
カスタマーストーリーのKPIツリー
以下がカスタマーストーリーのKPIツリーです。

カスタマーストーリーのKGIは予算達成(売上と利益)です。攻める営業活動をすることによって売上と利益を最大化させることがゴールです。
そしてそれを実現する成功要因KSFは「売上の増加」、「利益の増加」そして「費用の管理」です。
そして売上の増加というKSFの下には、それを実現するためのKPIがあります。KPI-1は「アカウント数」や「売上/アカウント」です。つまりアカウント数を増やしながら、ひとつのアカウントの売上を伸ばしていくという活動です。
KPI-1をさらに分解したものがKPI-2であり、「売上/アカウント」の下には、案件別予算というKPI-2があります。これがカスタマーストーリーのプロセスである、「リスト数」、「提案数」、「案件数」、「見積り数」、「受注数」というKPI-3になります。
このようにKPIツリーは分解できます。カスタマーストーリーについて詳しくは、以下のコラムをご参照ください。
■関連コラム
カスタマーエクスペリエンスのKPIツリー
以下がカスタマーエクスペリエンスのKPIツリーです。

カスタマーストーリーのKGIはオペレーショナルエクセレンスです。オペレーショナルエクセレンスとは、業務改善プロセスが現場に定着し、オペレーションが磨きあげられ、競争上の優位性にまでなっている状態です。 E2Eのカスタマーエクスペリエンス(顧客体験:CX=品質)とそれを支えるE2Eのバックプロセス(効率)の両方を最大化させることがゴールです。
つまりオペレーショナルエクセレンスを実現する成功要因KSFは「E2Eカスタマーエクスペリエンス」と「E2Eバックプロセス」です。
そしてE2Eカスタマーエクスペリエンス(CX)のKSFの下には、それを実現するためのKPIがあります。KPI-1は「顧客満足インデックス」や「NPS」です。そしてE2Eカスタマーエクスペリエンスを支えるもう一つのKSFの下には「Q:Quality(品質)」、「C:Cost(処理時間)」、「D:Derivery(PLT:Process Lead Time、つまり納期)」があります。
KPI-1をさらに分解したものがKPI-2であり、「E2ECX」側には、「内容確認」、「注文」、「支払」、「受取」、「使用開始」という顧客体験のプロセスが、「E2Eバックプロセス」側には、「コンテンツ提供」、「受注処理」、「請求入金」、「調達」、「受入出荷納品」、「サポート」という顧客体験を支えるオペレーションんのプロセスがあります。
このようにKPIツリーは分解できます。カスタマーエクスペリエンスについて詳しくは、以下のコラムをご参照ください。
■関連コラム
KPIのツリーをつくるメリット
いかがでしたでしょうか。KPIツリーについて理解ができたでしょうか。KPIツリーをつくることは様々なメリットがあります。
- 成功に必要なプロセスを読み解いてストーリーを共有する
KPIツリーは、別名ロジックツリーともいわれています。大きな目標であるKGIを成功要因で分析していく作業です。KPIツリーを作成するによってマネジメント層やプロジェクトの実行部隊全体が目標達成までのプロセスを論理的にに理解することができます。また可視化されることで目標の成功要因と進捗を共有することで共通認識を作り出すことができます。
- ボトルネックを見つけて改善する
KPIツリーは、目標達成を構成だてて論理的に見える化したストーリーです。論理的という部分をいいかえると成功のためのプロセスがあるということです。プロセスが出来ていれば目標達成への進捗であるKPIがおもったようにいかない場合に、プロセスの中の上手くいっていないプロセスはどこか、流れを詰まらせているボトルネックをつきとめて課題と根本原因を取り出し改善活動を行うことができます。プロセスからデータから継続的に改善を行っていくことができます。
- 各チームやメンバー責任が明確になる
KPIツリーはマネジメントやプロジェクトチーム、現場で作業する人たちの責任を明確にすることができるというメリットもあります。KPIツリーは分解できるので、各部門や役職などのレベルにあった目標を設定できるのです。例えば売上100億円が目標といってもマーケティングコミュニケーションを担当する現場の人にはピンと来ないかもしれません。でも今年の新規顧客獲得数の目標が1万人で5万人のリード獲得があなたの目標といわれると自身の日々の業務にあっていて納得感があると思います。5万人のリードを集め20%以上をカスタマーにする(20%のコンバージョンレート)ことに集中ことができる、自身の役割に集中して目標に邁進できるわけです。
■関連コラム
継続的に改善する
変化の多いスピードの速い世の中では継続的改善の重要性が高まります。継続的改善を行うためには以下のような基本的な考え方が前提になります。
- 顧客(VOC: Voice of Customer)にフォーカスする
- E2E(はじまりからおわりまで)のプロセスを見る
- QCD(Quolity:品質、Cost:コスト、Delivery:納期)に注目する
- 論理的に構造化された方法で改善をすすめる
- 上記の考え方を関わる人たちに根付かせる
継続的改善について詳しくは以下のコラムを参照してください。
■関連コラム(リンクのないコラムは近日公開予定です)

「図解!B2Bマーケティング戦略の作り方」eBook無料ダウンロード
マーケティング戦略とは、「誰に」、「何を」、「どうやって」提供して対価をもらうかということ。マーケティング戦略の基本をシンプルに理解できるeBookを無料で差し上げます。以下のフォームに記入して手にいれてください。